「意味がわかる」って、どういうこと?
ねえ、こんなふうに思ったことはありませんか?
「同じように授業を聞いて、宿題もやっているのに、あの子はなんでテストでいい点をとれるんだろう?」
「私もちゃんとノートをとっているのに、どうして全然覚えていないんだろう…」
もしかしたら、それは「意味がわかっているかどうか」の違いかもしれません。
今回は、「意味がわかる子」と「意味がわからない子」のちがいについて、わかりやすくお話します。
どうすれば“わかる子”になれるのかも、一緒に考えてみましょう。
ただ読むだけじゃ、もったいない!
たとえば、国語の授業でお話を読むとしますね。
「モチモチの木」や「スイミー」など、いろんなお話があります。
読み終わったあとに先生が聞きます。「このお話で大事なことは何だと思いますか?」
Aくん:「魚がいっぱい出てきた話です」
Bさん:「力を合わせると、できないこともできるってことだと思いました」
どちらのほうが「ちゃんと意味がわかっている」と感じますか?
そうです、Bさんのほうですね。
ただ読んだだけではなく、「作者が何を伝えたかったのか」まで考えています。
つまり、“読む”というのは、ただ文字を追うだけではなく、**「考えること」**がとても大切なのです。
勉強は、情報を集めるだけではありません
では、算数の場合はどうでしょう?
「3×4=12」と習ったとき、「はい、覚えました!」で終わる子もいれば、
「これは、3が4こあるってこと? じゃあ、4×3でも同じになるのかな?」と考える子もいます。
この“ちょっとした考える時間”が、とても大切なのです。
わかったつもりでも、「どういう意味なんだろう?」「なんでこうなるんだろう?」と疑問をもつことで、深く理解できるようになります。
つまり、「意味がわかる」というのは、頭を使って、自分の中にしっかり入れていくことなのです。
「意味がわかる子」がやっていること
意味がわかる子は、すごく特別なことをしているわけではありません。
ちょっとしたクセや習慣のちがいで、理解の深さが変わってきます。
たとえば…
① わからないときに「どうして?」と考える
ただスルーせずに、「これはなぜだろう?」と考えるクセがあります。
「夕日が赤いのはなぜ?」と理科で習ったとき、「へえ〜」で終わらせず、
「じゃあ朝日は? 夜は? 雲がある日は?」と、次の“?”を見つけることができます。
② わかりにくい言葉を、自分の言葉で言いかえる
たとえば「共通点」という言葉が出てきたとき、「あ、似ているところのことかな」と、心の中で自分の言葉に言いかえてみます。
そうすると、自分がよく知っている言葉になるので、忘れにくくなります。
③ 「前に習ったこととつながっているかな?」と思い出す
新しいことを習ったときに、「これは前にも出てきた内容かな?」と、思い出してみるのです。
知識がバラバラにならず、ひとつの線としてつながると、理解がぐっと深まります。
「わかる」って、実はとても気持ちがいい!
「勉強って、つまらないな」と思うこともありますよね。
でも、「あっ、そういうことだったのか!」とピンときた瞬間って、ちょっとうれしくなりませんか?
それは、脳が“わかったよ!”と光った瞬間なんです。
この「わかった!」という感覚を増やしていくことが、勉強を楽しむコツです。
そのために大事なのが、「考えること」「意味をつかもうとすること」なのです。
覚えるだけではなく、「なんで?」「どうして?」と自分の頭で動いてみる。
それだけで、勉強はどんどん面白くなります。
まとめ:あなたも「意味がわかる子」になれます
ここまでのお話をまとめると、こんなふうになります。
- 勉強ができる子は、「意味がわかる」までしっかり考えています
- ただ聞くだけ・読むだけでは、なかなか頭に残りません
- 「なんで?」「どういうこと?」と、ちょっと立ち止まって考えるクセをつけましょう
- わかりにくい言葉は、自分の言葉で言いかえてみましょう
- 勉強は“考えるゲーム”です。わかると気持ちがいいのです!
大丈夫です。あなたも今日から「意味がわかる子」になれます。
どんなに勉強ができるように見える子でも、最初は「なんで?」のくり返しからスタートしています。
ちょっとずつでかまいません。
「これって、どういうことだろう?」と考えるクセ、今日から始めてみませんか?


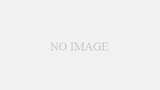

コメント